今回は宇治拾遺物語から「児のそら寝」について現代語訳・解説をしていきます。
このお話はある宵、僧たちがぼたもちを作ろうと話しているのを聞いた児が、寝たふりをしてできあがりを待っていました。
さて、児はぼたもちを食べることができたのでしょうか?
・児は何を期待して寝たふりをしたのか?
・児はなぜ1回で返事をしなかったのか?
・児はなぜ僧たちに大笑いされた?
・児の寝たふりはバレていたのか?
以上の内容に注目して、本文を見ていきたいと思います。
宇治拾遺物語「児のそら寝」品詞分解・現代語訳・解説

本文・品詞分解(語句解説)・現代語訳
これも今は昔、比叡の山に児ありけり。
| 語句 | 意味 |
| これ | 代名詞 |
| も | 係助詞 |
| 今 | 名詞 |
| は | 係助詞 |
| 昔、 | 名詞 |
| 比叡の山 | 名詞 |
| に | 格助詞 |
| 児 | 名詞 |
| あり | ラ行変格活用動詞「あり」連用形 |
| けり。 | 過去を表す助動詞「けり」の終止形 |
【訳】これも今は昔のことだが、比叡山延暦寺に児がいた。
「児」という語について
①赤ん坊、幼児、子ども
②寺院などに学問などを習得するために預けられていた少年
③神社や寺院の祭礼などの行列に加わる児童

ここでは②の意味で用いられています。
ちなみに枕草子の「うつくしきもの」では「瓜にかきたる児の顔」「頭は尼そぎなる児」などという表現がありますが、これは①の意味で用いられています。

「今は昔」というのは昔話の語り出しの、お決まりのパターンです。
文末は「けり」という過去を表す助動詞になっていることも、合わせておさえておきましょう。
僧たち、よひのつれづれに、「いざ、かいもちひせむ。」と言ひけるを、
| 語句 | 意味 |
| 僧たち、 | 名詞 |
| よひ | 名詞(日が暮れて間もない頃。または日が暮れてから、夜中までの間。) |
| の | 格助詞 |
| つれづれ | 名詞(退屈な様子。手持ち無沙汰なこと。) |
| に、 | 格助詞 |
| 「いざ、 | 感動し(さあ。さて。) |
| かいもちひ | 名詞(ぼたもち) |
| せ | サ行変格活用動詞「す」の未然形 |
| む。」 | 意志の助動詞「む」の終止形 |
| と | 格助詞 |
| 言ひ | ハ行四段活用動詞「言ふ」連用形 |
| ける | 過去の助動詞「けり」連武井 |
| を、 | 格助詞 |
【訳】僧たちが、宵の退屈さに、「さあ、ぼたもちを作ろう。」と言ったのを、

「よひ」って真夜中だと思ってました。
夜中にぼたもちを作るなんて、どんな状況だろうと思いました。

日が暮れて、大人たちが寝るまでの退屈しのぎにぼたもちを作ったということですね。
直訳すると「ぼたもちしよう」となります。

それだと日本語が変なので、「ぼたもちを作ろう」と訳されているのですね。
この児、心よせに聞きけり。
| 語句 | 意味 |
| こ | 代名詞 |
| の | 格助詞 |
| 児、 | 名詞 |
| 心よせ | 名詞(期待すること) |
| に | 格助詞 |
| 聞き | カ行四段活用動詞「聞く」連用形 |
| けり。 | 過去の助動詞「けり」終止形 |
【訳】この児は期待して聞いた。

児が「心よせ」にしていたのは、自分もぼたもちが食べられることですね。

そうですね。
「一緒に作りたい」のではなく、「できあがったぼたもちを食べたい」のですね。
さりとて、しいださむを待ちて寝ざらむも、わろかりなむと思ひて、
| 語句 | 意味 |
| さりとて、 | 接続詞(だからといって) |
| しいださ | サ行四段活用動詞「しいだす」(作り出す、作り上げる)未然形 |
| む | 婉曲の助動詞「む」の連体形 |
| を | 格助詞 |
| 待ち | タ行四段活用動詞「待つ」連用形 |
| て | 接続助詞 |
| 寝 | ナ行下二段活用動詞「寝(ぬ)」の未然形 |
| ざら | 打消の助動詞「ず」の未然形 |
| む | 仮定の助動詞「む」の連体形 |
| も、 | 係助詞 |
| わろかり | ク活用の形容詞「わろし」(良くない)の連用形 |
| な | 強調の助動詞「ぬ」(きっと~)の未然形 |
| む | 推量の助動詞「む」の終止形 |
| と | 格助詞 |
| 思ひ | ハ行四段活用動詞「思ふ」連用形 |
| て、 | 接続助詞 |
【訳】だからと言って、作り上がるのを待って寝ないのも、きっとみっともないだろうと思って、

直訳すると「作り上げるようなのを」となります。
日本語として不自然なので、婉曲にあたる「ような」の部分は省略しています。
わろし(良くない) < 悪し (悪い)
かたかたに寄りて、寝たるよしにて、いでくるを待ちけるに、
| 語句 | 意味 |
| かたかた | 名詞(片隅) |
| に | 格助詞 |
| 寄り | ラ行四段活用動詞「寄る」連用形 |
| て、 | 接続助詞 |
| 寝 | ナ行下二段活用動詞「寝」連用形 |
| たる | 存続の助動詞「たり」連体形 |
| よし | 名詞(そぶり。様子。) |
| にて、 | 格助詞 |
| いでくる | カ行変格活用動詞「いでく」(出来上がる)連体形 |
| を | 格助詞 |
| 待ち | タ行四段活用動詞「待つ」連用形 |
| ける | 過去の助動詞「けり」連体形 |
| に、 | 接続助詞 |
【訳】(部屋の)片隅に寄って、寝ているふりで、(ぼたもちが)できあがるのを待っていると、

「寝たるよし」は「寝ているふり」のことで、「そら寝」と同様の意味だとわかります。
すでにしいだしたるさまにて、ひしめきあひたり。
| 語句 | 意味 |
| すでに | 副詞(もう) |
| しいだし | サ行四段活用動詞「しいだす」(作り上げる。出来上がる)。連用形 |
| たる | 完了の助動詞「たり」連体形 |
| さま | 名詞(様子) |
| にて、 | 格助詞 |
| ひしめきあひ | ハ行四段活用動詞「ひしめきあふ」(大勢が集まって騒ぐ) |
| たり。 | 存続の助動詞「たり」終止形 |
【訳】もう出来上がった様子で、僧たちが集まって騒ぎ立てている。
この児、さだめておどろかさむずらむと待ちゐたるに、
| 語句 | 意味 |
| こ | 代名詞 |
| の | 格助詞 |
| 児、 | 名詞 |
| さだめて | 副詞(必ず。きっと。) |
| おどろかさ | サ行四段活用動詞「おどろかす」(起こす、目を覚まさせる)未然形 |
| むず | 推量の助動詞「むず」の終止形 |
| らむ | 現在推量(今頃~だろう)の助動詞「らむ」の終止形 |
| と | 格助詞 |
| 待ちゐ | ワ行上一段活用動詞「待ちゐる」(待っていた)連用形 |
| たる | 存続の助動詞「たり」連体形 |
| に、 | 格助詞 |
【訳】この児は、きっと(僧たちが自分のことを)起こすだろうと待っていたところ、
僧の、「もの申しさぶらはむ。おどろかせたまへ。」と言ふを、
| 語句 | 意味 |
| 僧 | 名詞 |
| の、 | 格助詞 |
| 「もの | 名詞 |
| 申し | 【謙譲】サ行四段活用動詞「申す」連用形(僧たち→児への敬意) |
| さぶらは | 【丁寧】ハ行四段活用補助動詞「さぶらふ」の未然形(僧たち→児への敬意) |
| む。」 | 意志の助動詞「む」終止形 |
| おどろか | カ行四段活用動詞「おどろく」(目を覚ます)の未然形 |
| せ | 尊敬の助動詞「す」の連用形 |
| たまへ。」 | 【尊敬】ハ行四段活用補助動詞(~なさる)「たまふ」命令形(僧たち→児への敬意) |
| と | 格助詞 |
| 言ふ | ハ行四段活用動詞「言ふ」連体形 |
| を、 | 格助詞 |
【訳】僧が、「もしもし。目をお覚ましなさいませ。」と言うのを、

「もの申しさぶらはむ。」…直訳すると「ものを申し上げましょう」となります。
ここでは、丁寧に呼びかける際の慣用表現「もしもし」として覚えてましょう。

僧たちが児に対して、敬語を使っているのはなぜですか?
児とは?
平安時代「貴族が学問や行事の見習いのために寺院に預けた子ども」を指す。
または観音菩薩の化身として扱われていたとも言われている。

良いところのお坊ちゃんをお預かりしているので、僧たちは児に対して敬語を使っていたのですね。

僧たちにとって児は「尊い存在として扱う相手」でした。
うれしとは思へども、
| 語句 | 意味 |
| うれし | シク活用の形容詞「うれし」終止形 |
| と | 格助詞 |
| は | 係助詞 |
| 思へ | ハ行四段活用動詞「思ふ」已然形 |
| ども、 | 接続助詞 |
【訳】(児は)うれしいとは思ったが、
ただ一度にいらへむも、待ちけるかともぞ思ふとて、
| 語句 | 意味 |
| ただ | 副詞 |
| 一度 | 名詞 |
| に | 格助詞 |
| いらへ | ハ行下二段活用動詞「いらふ」(返事をする)未然形 |
| む | 仮定の助動詞「む」連体形 |
| も、 | 係助詞 |
| 待ち | タ行四段活用動詞「待つ」連用形 |
| ける | 過去の助動詞「けり」連体形 |
| か | 係助詞 |
| と | 格助詞 |
| も | 係助詞 |
| ぞ | 係助詞 |
| 思ふ | ハ行四段活用動詞「思ふ」連体形 |
| とて、 | 格助詞 |
【訳】すぐ一度で返事をするのも、(起こされるのを)待っていたかと(僧たちが)思っては困ると考え、

この児の考えていることをどう思いますか?

ぼたもちの完成を待ちわびていて、すぐにでも食べたいだろうに、1回で返事をしないのは、子どもらしくないと思いました。
「待っていたと思われるのが良くない」と言うのも、児のプライドのようなものを感じました。

ここで先ほどの「児=良いとこの坊ちゃん」というのがポイントになってきます。
僧たちから敬語を使われ、尊い者としての扱いを受ける一方、児もその扱いにふさわしいような、優雅で高貴な振る舞いをしようという気持ちを持っているんですね。

だから自分から「ぼたもちできた?食べたいよ!」なんて言うことはもちろん、それを寝たふりをして待つというのも、みっともないことだと考えるんですね。

「できました。どうぞお召し上がりください。」と言われて、
「そうか、そういうなら食べてみようか」という余裕のある対応が望ましいと思ったのでしょう。
「や、な起こしたてまつりそ。をさなき人は寝入りたまひにけり。」と言ふこゑのしければ、
| 語句 | 意味 |
| 「や、 | 感動詞 |
| な | 副詞 |
| 起こし | サ行四段活用動詞「起こす」(目を覚まさせる)連用形 |
| たてまつり | 【謙譲】ラ行四段活用補助動詞「たてまつる」連用形 |
| そ。 | 終助詞 |
| をさなき | ク活用の形容詞「おさなし」(幼い) |
| 人 | 名詞 |
| は | 係助詞 |
| 寝入り | ラ行四段活用動詞「寝入る」連用形 |
| たまひ | 【尊敬】ハ行四段活用補助動詞「たまふ」(~なさる)連用形(僧たち→児への敬意) |
| に | 完了の助動詞「ぬ」連用形 |
| けり。」 | 過去の助動詞「けり」終止形 |
| と | 格助詞 |
| 言ふ | ハ行四段活用動詞「言ふ」連体形 |
| こゑ | 名詞 |
| の | 格助詞 |
| し | サ行変格活用動詞「す」連用形 |
| けれ | 過去の助動詞「けり」已然形 |
| ば、 | 接続助詞 |
【訳】「おい、お起こし申し上げるな。幼い人は寝入りなさってしまった。」と言う声がしたので、
あなわびしと思ひて、いま一度起こせかしと思ひ寝に聞けば、
| 語句 | 意味 |
| あな | 感動詞(ああ。) |
| わびし | シク活用の形容詞「わびし」(困ったことだ)終止形 |
| と | 格助詞 |
| 思ひ | ハ行四段活用動詞「思ふ」連用形 |
| て、 | 接続助詞 |
| いま | 副詞(さらに。もう。) |
| 一度 | 名詞 |
| 起こせ | サ行四段活用動詞「起こす」命令形 |
| かし | 【念押し】終助詞(~よ) |
| と | 格助詞 |
| 思い寝 | 名詞(思い続けながら寝ること) |
| に | 格助詞 |
| 聞け | カ行四段活用動詞「聞く」已然形 |
| ば、 | 接続助詞 |
【訳】ああ困ったことだと思って、もう一度起こしてくれよと思い続けながら寝て聞いていると、

児の思う通りにいかなかったみたいですね…

そうですね。
「あなわびし」と嘆き、「いま一度起こせかし」と願います。
この「あな」は喜怒哀楽どの感情に対しても使うことができます。
「あな」「かし」から児の切なる思いが感じられます。
「頼むからもう一回起こしに来て!!」と言った感じでしょうか。
ひしひしとただ食ひに食ふ音のしければ、
| 語句 | 意味 |
| ひしひしと | 副詞(むしゃむしゃと) |
| ただ | 副詞(ひたすら~する) |
| 食ひ | ハ行四段活用動詞「食ふ」連用形 |
| に | 格助詞 |
| 食ふ | ハ行四段活用動詞「食ふ」連体形 |
| 音 | 名詞 |
| の | 格助詞 |
| し | サ行変格活用動詞「す」連用形 |
| けれ | 過去の助動詞「けり」已然形 |
| ば、 | 格助詞 |
【訳】むしゃむしゃとひたすらに食べる音がしたので、

「食ひに食ふ」は直訳すると「食べに食べる」です。

これは現代でも「笑いに笑った」「走りに走った」などと使いますね。

強調するときに使われる表現です。
ここでは「ただ」という「ひたすら~する」という語も使われているので、
「ひたすら食べる音がした」と現代語訳してOKです。
ずちなくて、無期ののちに、
| 語句 | 意味 |
| ずちなく | ク活用の形容詞「ずちなし」(どうしようもない)の連用形 |
| て、 | 接続助詞 |
| 無期 | 名詞(その状態が長く続いたこと。長時間がたったこと。) |
| の | 格助詞 |
| のち | 名詞(あと) |
| に、 | 格助詞 |
【訳】どうしようもなくて、長時間経ったあとに、

児は「ぼたもちが食べ尽くされてしまう」と、不安になってしまう状況だったことは間違いないですね!
「えい。」といらへたりければ、
| 語句 | 意味 |
| 「えい。」 | 感動詞(はい) |
| と | 格助詞 |
| いらへ | ハ行下二段活用動詞「いらふ」連用形 |
| たり | 完了の助動詞「たり」連用形 |
| けれ | 過去の助動詞「けり」已然形 |
| ば、 | 接続助詞 |
【訳】「はい。」と返事をしたので、
僧たちわらふことかぎりなし。
| 語句 | 意味 |
| 僧たち | 名詞 |
| わらふ | ハ行四段活用動詞「わらふ」連体形 |
| こと | 名詞 |
| かぎりなし。 | ク活用の形容詞「かぎりなし」(はなはだしい。この上ない。)終止形 |
【訳】僧たちは笑うことがこの上ない。

結局、我慢できずに自分から出て行っちゃいましたね。

立派な態度でぼたもちを待とうと思ったものの、思うようにいかず、最終的には食べたい気持ちが勝って、返事をしました。

僧たちはどうして大爆笑したんですか?

「子どもの癖にかっこつけて我慢しようとするなんて」と馬鹿にしているわけではありません。
「大人びた態度をとろうとしたけど、ぼたもち食べたさに返事をする児の子供らしさがかわいらしい」という状況ではないでしょうか。

児の寝たふりって僧たちにバレてたんですかね?

本文は児の視点から書かれているので、
僧たちが知っていたかは明確ではありません。
しかし僧たちが児の寝たふりに気付いていて、「もう起こすな」と児をからかっていたとしたらどうでしょう。
その後、児が「はい」と答えたら、大爆笑してしまう僧たちの気持ちも理解できます。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は宇治拾遺物語より「児のそら寝」を解説しました。
→僧たちが作ったぼたもちができあがったら食べること
・児はなぜ1回で返事をしなかったのか?
→すぐに返事をするのは寝たふりをして待っていたと思われる、みっともないことだと考え、大人びた振る舞いをしようとしたから。
・児はなぜ僧たちに大笑いされた?
→大人びた振る舞いをしようと我慢していた児が、僧に声をかけられてしばらくたった後に返事をしたから。
それらを僧たちは、子どもらしくてかわいらしいと思ったのではないか。
・児の寝たふりはバレていたのか?
→明言はないが、その可能性も大いにある。
ポイントはおさえられたでしょうか?
古文は一文が長く読みにくかったり、文法や単語など覚えることが多く苦手意識を持つ方も多いかもしれません。
丁寧に読んでいきましょう。


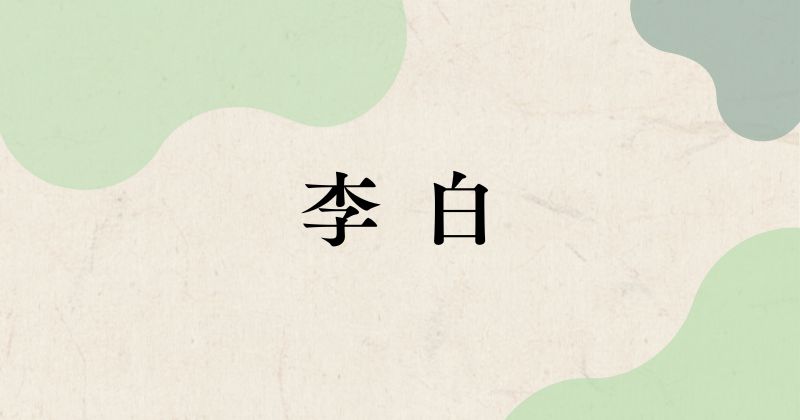

コメント