徒然草より第三十二段「九月二十日のころ」について解説をしていきます。
徒然草は鎌倉時代の作品で、兼好法師が見聞きしたもの、感じたことなどを思うままに書き綴った作品です。
世の無常を感じて出家した兼好法師は、どうなるかわからない先のことを嘆くより、今を大切にするべきだと語っています。
今回のお話は、主語が省略されている部分が多いので、補いながら現代語訳と解説していきます。
読みながら場面を理解していきましょう。
この記事では
・本文(読み仮名付き)
・品詞分解と語句解説
・現代語訳
・本文の解説
以上の内容を順番にお話していきます。
徒然草「九月二十日のころ」品詞分解・現代語訳・解説

本文・品詞分解(語句解説)・現代語訳
九月二十日のころ、ある人に誘はれ奉りて、
| 語句 | 意味 |
| 九月二十日 | 名詞 |
| の | 格助詞 |
| ころ、 | 名詞 |
| ある | 連体詞 |
| 人 | 名詞 |
| に | 格助詞 |
| 誘は | ハ行四段活用動詞「誘ふ」未然形 |
| れ | 受身の助動詞「る」の連用形 |
| 奉り | ラ行四段活用動詞「奉る」連用形(~申し上げる、~し申す)【謙譲】作者→ある人への敬意 |
| て、 | 接続助詞 |
【訳】9月20日のころ、ある人にお誘いいただいて、
明くるまで月見歩くこと侍りしに、
| 語句 | 意味 |
| 明くる | カ行下二段活用動詞「明く」(明ける)連体形 |
| まで | 副助詞 |
| 月 | 名詞 |
| 見歩く | カ行四段活用動詞「見歩く」(見て回る)連体形 |
| こと | 名詞 |
| 侍り | ラ行変格活用動詞「侍り」連用形(あります、ございます)【丁寧】作者→読者への敬意 |
| し | 過去の助動詞「き」連体形 |
| に、 | 接続助詞 |
【訳】(夜が)明けるまで月を見てまわることがございましたが、
思し出づるところありて、案内せさせて入り給ひぬ。
| 語句 | 意味 |
| 思し出づる | ダ行下二段活用動詞「思し出づ」(お思い出しになる)連体形【尊敬】作者→ある人への敬意 |
| ところ | 名詞 |
| あり | ラ行変格活用動詞「あり」連用形 |
| て、 | 接続助詞 |
| 案内せ | サ行変格活用動詞「案内す」未然形 |
| させ | 使役の助動詞「さす」の連用形 |
| て | 接続助詞 |
| 入り | ラ行四段活用動詞「入る」連用形 |
| 給ひ | ハ行四段活用補助動詞「給ふ」(お~になる)連用形【尊敬】作者→ある人への敬意 |
| ぬ。 | 完了の助動詞「ぬ」の終止形 |
【訳】(ある人が)お思い出しになった所があって、(自分のお供に)取り次がせて(その家の中に)お入りになった。

「九月二十日」とは陰暦なので、現在では10月下旬から11月初旬頃と考えられます。

朝晩の冷えを感じ、月がはっきりと見える時期でもありますね。
・ある人
・作者
・ある人のお供の者
・その人

ここで言う「ある人」は男性です。
立ち寄ったのは女性(その人)の家ということを、最初におさえておいてください。
登場人物を把握しながら、主語を補っていきましょう。
荒れたる庭の露しげきに、
| 語句 | 意味 |
| 荒れ | ラ行下二段活用動詞「荒る」(荒れる)連用形 |
| たる | 存続の助動詞「たり」連体形 |
| 庭 | 名詞 |
| の | 格助詞 |
| 露 | 名詞 |
| しげき | ク活用の形容詞「しげし」(たくさんある)連体形 |
| に、 | 接続助詞 |
【訳】荒れている庭で露がたくさん降りていて、
わざとならぬにほひ、しめやかにうち薫りて、
| 語句 | 意味 |
| わざと | 副詞(わざわざ) |
| なら | 断定の助動詞「なり」未然形 |
| ぬ | 打消の助動詞「ず」連体形 |
| にほひ、 | 名詞 |
| しめやかに | ナリ活用の形容動詞「しめやかなり」(もの静かだ)連用形 |
| うち薫り | ラ行四段活用動詞「うち薫る」(ほんのりとよい香りがする)連用形 |
| て、 | 接続助詞 |
【訳】わざわざ(たいたとも)思えない香りが、もの静かにほんのりと良い香りがして、
忍びたるけはひ、いとものあはれなり。
| 語句 | 意味 |
| 忍び | バ行上二段活用動詞「忍ぶ」(人目につかないようにする)連用形 |
| たる | 存続の助動詞「たり」連体形 |
| けはひ、 | 名詞(様子) |
| いと | 副詞(本当に) |
| ものあはれなり。 | ナリ活用の形容動詞「ものあはれなり」(なんとなくしみじみと感じる)終止形 |
【訳】(その人が)人目を避けてひっそりと住んでいる様子が、本当になんとなくしみじみと情緒を感じる。
よきほどにて出(い)で給ひぬれど、
| 語句 | 意味 |
| よき | ク活用の形容詞「よし」連体形 |
| ほど | 名詞(時分、時間) |
| にて | 格助詞 |
| 出で | ダ行下二段活用動詞「出づ」連用形 |
| 給ひ | ハ行四段活用補助動詞「給ふ」連用形【尊敬】作者→ある人への敬意 |
| ぬれ | 完了の助動詞「ぬ」已然形 |
| ど、 | 接続助詞 |
【訳】(ある人は)ほど良い時間にお出になったが、
なほことざまの優におぼえて、物の隠れよりしばし見ゐたるに、
| 語句 | 意味 |
| なほ | 副詞(やはり) |
| ことざま | 名詞(物事の様子、ありさま) |
| の | 格助詞 |
| 優に | ナリ活用の形容動詞「優なり」(優美だ、優雅だ)連用形 |
| おぼえ | ヤ行下二段活用動詞「おぼゆ」(思われる)連用形 |
| て、 | 接続助詞 |
| 物 | 名詞 |
| の | 格助詞 |
| 隠れ | 名詞(人目につきにくい所、物陰) |
| より | 格助詞 |
| しばし | 副詞(しばらく) |
| 見 | マ行上一段活用動詞「見る」連用形 |
| ゐ | ワ行上一段活用動詞「ゐる」(~し続ける)連用形 |
| たる | 完了の助動詞「たり」連用形 |
| に、 | 接続助詞 |
【訳】(私は)やはり(その人の)事のありさまが優雅に思われて、物陰からしばらく見続けていると、
妻戸をいま少し押し開けて、月見る気色なり。
| 語句 | 意味 |
| 妻戸 | 名詞(建物の端について両開きの戸のこと) |
| を | 格助詞 |
| いま | 副詞(さらに) |
| 少し | 副詞 |
| 押し開け | カ行下二段活用動詞「押し開く」連用形 |
| て、 | 接続助詞 |
| 月 | 名詞 |
| 見る | マ行上一段活用動詞「見る」連体形 |
| 気色 | 名詞(様子) |
| なり。 | 断定の助動詞「なり」終止形 |
【訳】(その人が)妻戸をさらに少し押し開けて、月を見る様子である。
やがてかけこもらましかば、口惜しからまし。
| 語句 | 意味 |
| やがて | 副詞(すぐに) |
| かけこもら | ラ行四段活用動詞「かけこもる」(かぎをかけて閉じこもる)未然形 |
| ましか | 反実仮想の助動詞「まし」(もし~だったら…だろう)未然形 |
| ば、 | 接続助詞 |
| 口惜しから | シク活用の形容詞「口惜し」(残念だ)未然形 |
| まし。 | 反実仮想の助動詞「まし」終止形 |
【訳】もし(その人が妻戸の)掛け金をかけて部屋にこもってしまったとしたら、残念だったことだろう。

「その人」が客である「ある人」の帰った後も、すぐには部屋にこもらず、
月を眺めながら余韻を味わっています。
兼好は、その様子が素晴らしいと言っています。
あとまで見る人ありとは、いかでか知らん。
| 語句 | 意味 |
| あと | 名詞 |
| まで | 副助詞 |
| 見る | マ行上一段活用動詞「見る」連体形 |
| 人 | 名詞 |
| あり | ラ行変格活用動詞「あり」終止形 |
| と | 格助詞 |
| は、 | 係助詞 |
| いかで | 副詞(どうして~か、いや~ない)【反語】 |
| か | 係助詞【反語】 |
| 知ら | ラ行四段活用動詞「知る」未然形 |
| ん。 | 推量の助動詞「む」連体形 |
【訳】(ある人が帰った)後まで(自分を)見ている人がいるとは、(その人は)どうして知るだろうか、いや知らないだろう。
かやうのことは、ただ朝夕の心づかひによるべし。
| 語句 | 意味 |
| かやう | ナリ活用の形容動詞「かやうなり」の語幹(このよう) |
| の | 格助詞 |
| こと | 名詞 |
| は、 | 係助詞 |
| ただ | 副詞(ただもう) |
| 朝夕 | 名詞(毎日) |
| の | 格助詞 |
| 心づかひ | 名詞(心配り) |
| に | 格助詞 |
| よる | ラ行四段活用動詞「よる」終止形 |
| べし。 | 推量の助動詞「べし」の終止形 |
【訳】このようなことは、ただもう常日頃の心配りによるものだろう。

見られていると気付いていてとった態度ではないということは、日ごろからそのような過ごし方をしているのだろうということですね。

「かやうのこと」とは、「その人」が客人が帰ったあとも月を眺めて余韻を味わっていることを指します。
その人、ほどなく失せにけりと聞き侍りし。
| 語句 | 意味 |
| そ | 代名詞 |
| の | 格助詞 |
| 人、 | 名詞 |
| ほどなく | ク活用の形容詞「ほどなし」(連用形 |
| 失せ | サ行下二段活用動詞「失す」(連用形 |
| に | 完了の助動詞「ぬ」連用形 |
| けり | 過去の助動詞「けり」終止形 |
| と | 格助詞 |
| 聞き | カ行四段活用動詞「聞く」連用形 |
| 侍り | ラ行変格活用動詞「侍り」連用形【丁寧】作者→読者への敬意 |
| し。 | 過去の助動詞「き」連体形 |
【訳】ますます物事は(前もって)決めることが難しい。

この一文から、この章段は作者が過去のことを思い出し、「その人」をしのんで書かれていることが分かります。
→余韻を感じさせている

奥ゆかしくて素敵な女性が、亡くなってしまった…と惜しんでいる気持ちが感じられます。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は徒然草より「九月二十日のころ」を解説しました。
ある人と一緒に月見をして歩き回っていた作者。
ある人が立ち寄った女性の家の様子や振る舞いは、優雅で奥ゆかしく、素晴らしいものでした。
「その人、ほどなく失せにけりと聞き侍りし。」という一文でその思いを表現しています。
古文では主語が省略されていることが多く、場面を理解するのが難しく感じがちです。
こうして丁寧に読んでいくことで、場面を理解できたのではないでしょうか?


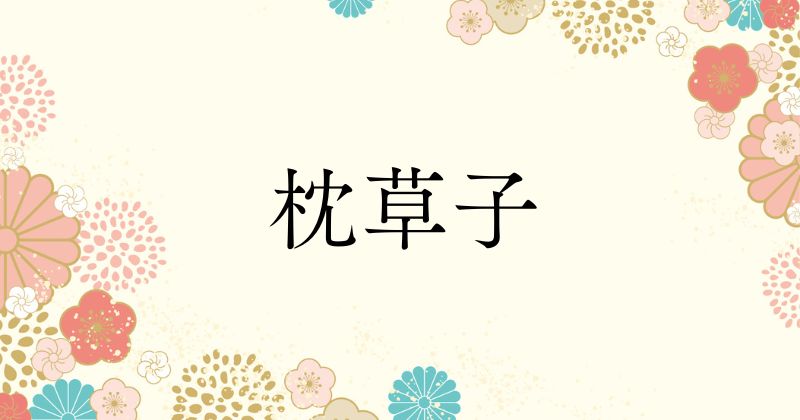
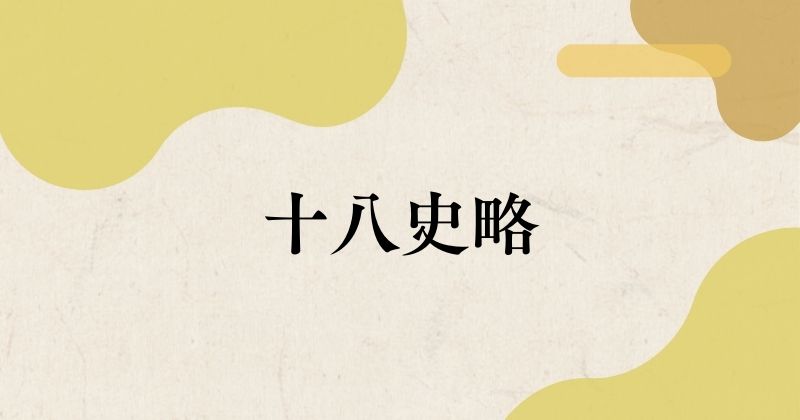
コメント
わかりやすくてありがたいです!
テストに出るので使わせていただきます!
コメントありがとうございます。
嬉しいです!励みになります。
今後ともお役に立てる内容をさらに目指していきます!